ビタミンB群とは水溶性のビタミンです。
ビタミンB群のような水溶性ビタミンは体内に蓄積されるビタミンA.D.E.Kのような脂溶性ビタミンとは違い過剰摂取しても体外に排出されます。
水溶性ビタミンにはビタミンB群の他にビタミンCがあります。
今回はビタミンB群の種類と効能について説明していきます。
目次
♡ビタミンB群とは?
ビタミンB群とは以下のビタミンになります。
・ビタミンB1
・ビタミンB2
・ビタミンB6
・ビタミンB12
・ナイアシン
・パントテン酸
・葉酸
・ビオチン
この8つがビタミンB群です。
8つそれぞれに違った効能があるので説明していきますね。
♡ビタミンB1

ビタミンB1には、ごはんやパンだけでなく砂糖などの糖類を分解しエネルギーにしてくれるはたらきがあります。
このB1が不足すると、いくら糖質を摂取してもエネルギーに変えることができません。
その結果、疲れやすくなったり精神が不安定になりイライラしたりします
また集中力がなくなるだけてなく、肝臓や腎臓などの臓器の機能が弱まり胃腸障害などの原因にもなります。
《B1を多く含む食材》
パン酵母、米ぬか、豚肉、レバー、豆類
♡ビタミンB2

脂質や糖質の代謝を促進してくれる働きがあります。脂質や糖質を分解しエネルギーにする効能があります。
また動脈硬化や老化の原因となる有害物質が体内でできるのを防いでくれるため生活習慣病の予防が期待できます。
このビタミンB2が不足すると肌荒れ、口内炎、口角炎、目の充血、抜け毛など皮膚や粘膜に障害がでてきます。
《B2を多く含む食材》
豚レバー、鳥レバー、豚肉、うなぎ、魚肉ソーセージ
♡ビタミンB6

皮膚や髪の毛、歯を健康にし成長を助ける働きがあります。
その他には生理などによる女性特有のホルモンバランスのくずれなども緩和してくれます。
ビタミンB6が不足すると以下のことがおこります。
・皮膚炎
・口内炎
・湿疹や蕁麻疹などの肌トラブル
・アレルギー症状がでやすくなる
などからみてもビタミンB6は免疫力維持するのに重要な栄養素だなと思います。
《B6を多く含む食材》
にんにく、バナナ、マグロ、さんま、ジャガイモ
♡ビタミンB12
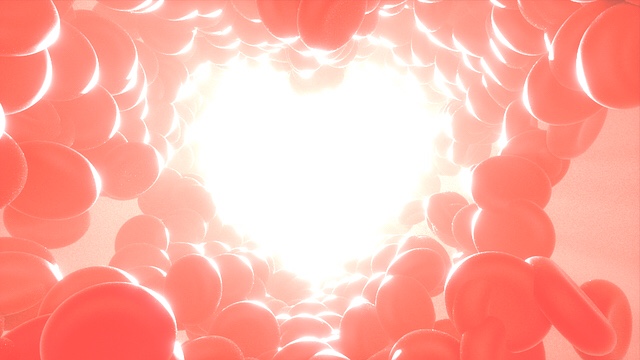
ビタミン12は葉酸と協力し赤血球が正常に分化するのを助けてくれます。
このビタミンが不足してしまうと悪性貧血になってしまうおそれがあります。
ビタミン12は過剰に摂取しても必要以上に吸収されることはありません。
《B12を多く含む食材》
しじみ、アカガイ、牛レバー、すじこ
♡葉酸

ビタミンB12と協力し赤血球を正常に分化するのを助けます。
また葉酸は細胞分裂で重要な役割をします。
葉酸が不足すると貧血だけでなく免疫力がおち病気をしやすくなります。
また妊娠中や授乳中に不足すると胎児や乳児の発育不全をひきおこすとも言われています。ビタミン12と摂取することで効果を発揮するので一緒に摂取した方がいいですね。
《葉酸を多く含む食材》
枝豆、モロヘイヤ、パセリ、芽キャベツ
♡ナイアシン
ナイアシンは糖質・脂質・たんぱく質の代謝に不可決なだけでなく、循環系・消化系・神経系の働きを促進する働きがあります。
このビタミンが不足すると皮膚炎や口内炎、神経炎などの症状がでることも。
お酒を飲む人は2日酔いなどの原因となるアセトアルデヒドの分解してくれる効果があるため摂取量が多いほど消費されるので不足しないように気をつけましょう。
《ナイアシンを多く含む食材》
たらこ、まぐろ、めんたいこ、かつお、まいたけ
♡パントテン酸

パントテン酸はビタミンB5ともよばれています。
この栄養素は体内でも合成することができ、三大栄養素である糖質・脂質・たんぱく質のエネルギー変換する時に重要な役割をはたします。
このパントテン酸が不足すると、疲れやすい、ストレスがたまる、風邪をひきやすくなったりします。
《パントテン酸を多く含む食材》
レバー、納豆、卵黄、干し椎茸、脱脂粉乳
♡ビオチン

ビオチンはアミノ酸の生成に関わる栄養素で、育毛効果なども期待されています。
そのほかにも、皮膚炎や抜け毛、白髪などを予防してくれる効果があります。
このビオチンが不足すると、疲れやすくなったり湿疹などの皮膚炎などの症状のほかに脂肪の代謝が悪くなったりします。
《ビオチンを多く含む食材》
まいたけ、らっかせい、たまご、きくらげ
以上がビタミンB群になります。
免疫力やエネルギーをつくるのにかかせないビタミンなので積極的に摂取したいですね(^^)









コメントを残す